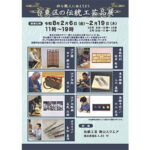1月12日から青山スクエアでは企画展「女一代のわざ 女性伝統工芸士展 作家とともに」が始まり、
14時からは恒例のトークショーが行われました。
今回は出展者数も多いということもあり、
トークショーはこれまでの中でも最長の2時間。
それでも、みなさん楽しげに、そして熱心にお話をしていただけました。
始めは西陣織の作り手さんから。

西陣織の野元博美さん
この道40年になる野元さんが得意としているのは、
つづれ織りです。
つづれ織りは、爪の先をギザギザにして横糸を詰め、
さらに柘植櫛でも横糸を詰めます。
こうした糸を使うことで、
つづれ織りの繊細さが表現できるそうです。
またインタビュアから西陣織の価格はどうやって決めているのかと質問されると、
その対象物に対してどれだけ時間を使ったのかによって変わるので、
対象物と価格を見て、
これがどうやって作られたのかが価格を見れば、
だいたいわかるとおっしゃっていました。
次に烏城紬の作り手さんが、話をしてくださいました。

烏城紬の須本雅子さん
200年の歴史のある烏城紬ですが、
現在作り手は須本さんだけになっています。
今は須本さんご自身が教室を開いており、
生徒さん達に伝統の技術を継承しているとおっしゃっていました。
烏城紬はもともと綿で出来たものしかなかったのですが、
須本さんのお爺さんが絹を取り入れるようになり、
今の烏城紬が出来るようになったそうです。
着物が主な製品ではあるものの、
最近はあえて余分な端切れが出るように作り、
端切れで財布やカード入れ等も作っているとおっしゃっていました。
続いて京繍の作り手さんにお話しいただきました。

京繍の山下憲子さん
京繍の刺繍の仕方は数多く存在します。
山下さんは、それらすべてを覚えるよりも、
基本の刺繍を覚えたら、
後は自分流の方法を見つけていく方が京繍の魅力が上がっていくとおっしゃっていました。
また山下さんは、
子どもの頃から京繍をしており、
学校から帰ってきたら京繍をするというのが日課で、
気が付くと仕事として行うようになっていたそうです。
京繍はそれほど、ご自身の日常の中の一つなのでしょう。
続いて美濃焼の作り手さんに、お話をしていただきました。

美濃焼の加藤音さん
美濃焼は岐阜県の東の方にある土岐市などで作られています。
加藤さんは自然の風景を表現するのが好きで、
陶器には葉っぱを貼りつけて焼成したものが数多くあります。
作る時のポイントとしては、
日常使いをしてもらえるために、
使い易さを追究したり、
食べ物を乗せた時にようやく完成するような器(装飾しすぎない)を追求しているそうです。
また実際に自分で使ってみて、
ここが使い易いとか、ここが使い辛いとかの研究を重ねているとおっしゃっていました。
続いて、九谷焼の作り手さんにお話をしていただきました。

九谷焼の平野由佳さん
平野さんは11年の修業を終え、
この世界で作り始めました。
日常で使って頂ける様にと、
絵付けに使う色にこだわっています。
平野さんが使っている色は中間色。
この色を使うことで、
主張しすぎない食器や置物ができるそうです。
今後は繊細な絵付けにも挑戦していきたいとおっしゃっていました。
続いて三川内焼の作り手にお話をしていただきました。

三川内焼の中里由美子さん
三川内焼は平戸の御用窯として発展しました。
三川内焼は2016年4月に日本遺産として認定され、
その後はメディアなどでも多く取り上げられるようになったそうです。
中里さんは絵付けを専門にしていますが、
形を作っているのは夫で、
営業や雑用をしているのが息子だとおっしゃっていました。
今後の目標としては、
龍の絵のバリエーションを広げていきたいそうです。
続いて、伊万里・有田焼の作り手さんにお話しして頂きました。

伊万里・有田焼の梶原真理江さん
梶原さんは伊万里・有田焼の中でも、
絵付けを担当しています。
もともと野の花が好きで、
そればかりを描いていました。
ですが、インパクトが弱いかもしれないと思い、
他の絵も描くようになったそうです。
けれど最近は、
また野の花を描くように。
身近なところに、たくさんの表情を魅せてくれる野の花があるからかもしれません、
今後も野の花を描き続けていきたいとおっしゃっていました。
続いて京くみひもの作り手さんにお話をしていただきました。

京くみひもの結城和子さん
京くみひもは本来、
ステイタスを示すためのものとして存在していたのですが、
明治以降に帯締めのために作られるようになりました。
そんな歴史がある京くみひものイメージを変えていきたいと思っているのが、
結城さん。
現在は神社仏閣で使われるくみひもをメインで作っていますが、
くみひもの巾着や信玄袋などを作り、
新しい可能性に取り組んでいます。
続いて奈良筆の作り手さんにお話をしていただきました。

奈良筆の田中千代美さん
奈良筆は最初から最後までの全工程を、
一人で行います。
羊毛筆と言われるものもあれば、
馬の尻尾の毛を混ぜたり、
狸の毛を混ぜて作る筆もあるそうです。
玄人になっていくと、
毛先の柔らかいもので書きますが、
初心者には硬い筆がおすすめ。
価格も硬い筆先のものであれば3000円ぐらいのものが、
良いとおっしゃっていました。
続いて、山中漆器の作り手さんにお話をしていただきました。

山中漆器の井尻美年子さん
井尻さんは山中漆器の中でも蒔絵師をしています。
絵を描くことが好きな井尻さんは、
アクセサリー(山中漆器)でも絵を描き込み過ぎてしまうのだとか。
わかっているけれど、止められず、
毎回、自分が楽しいと思えるところまで書き込みをしているそうです。
今後は、もっとメルヘンな世界観のあるものを、
山中漆器で表現していきたいと、おっしゃっていました。
続いて、広瀬絣の作り手さんにお話をしていただきました。

広瀬絣の永田佳子さん
広瀬絣の糸は木綿で、
昔は作業着として作られていました。
広瀬絣の藍は、
徳島県の藍を使っています。
永田さん自身も藍を4つ管理しているそうで、
藍の機嫌伺はとても大変そうです。
広瀬絣も後継者に悩んでいる産地で、
現在永田さんは教室を開いて、
広瀬絣の技の継承を行っているとおっしゃっていました。
続いて、村上木彫堆朱の作り手さんにお話をしていただきました。

村上木彫堆朱の池野律子さん
村上木彫堆朱には堆朱の他に、
堆黒や蒟醤(きんま)といった手法もあります。
池野さんの家でも、堆黒や蒟醤も行っているそうです。
村上木彫堆朱をしていると、
よく聞かれるのが、
鎌倉彫との違い。
鎌倉ではノミを使って木地を彫りますが、
村上ではうらじろと呼ばれる刃が両面についているもので彫ります。
そのため、村上の彫刻の方が細かく繊細な表現ができる、
という違いがあるのです。
また池野さんはこれまで彫りをしてきませんでしたが、
村上の事情として彫師が少ないということもあり、
去年の11月からは習い始めたそうです。
今後は、彫りでも一人前になっていきたいと、
おっしゃっていました。
続いて京友禅の作り手の方にお話をしていただきました。

京友禅の大石和泉さん
京友禅は8工程を昔から分業で行っており、
大石さんはその中でも、彩色工程を担当しています。
この道45年になったため、
何でも描けるようになりましたが、
今でも人物描写だけは苦手だそうです。
また京友禅は、
学校があるため若い人に人気があります。
ですが、卒業しても就職先が、
なかなか見つからないという難点も抱えているそうです。
大石さんのところにもお弟子さんが一人いたそうですが、
今はお嫁に行ってしまったため、
今は弟子がいない状態だとおっしゃっていました。
続いて山中漆器の作り手さんにお話をしていただきました。

山中漆器の大下香苑さん
大下さんは山中漆器のブランド「Classic Ko」を立ち上げ、
家族全員で作っています。
その他に万年筆の大手ブランド二社の蒔絵も担当しており、
忙しい日々を過ごしているそうです。
そんな大下さんが一番難しいと感じているのは、
デザイン。
蒔絵を描いていると、どんどんと描き込みたくなるものの、
多くの人に受け入れられるセンスのいいものを作るためには、
空白の美が重要だと考えているそうです。
アクセサリーは人が主役になるように作ることが、
最も大事なことだと、おっしゃっていました。
続いて、多摩織の作り手さんにお話をしていただきました。

多摩織の澤井恵子さん
多摩織は東京の八王子市で作られている、
伝統的工芸品です。
澤井さんの夫は、多摩織の四代目で、
澤井さん自身も作り手として活躍しています。
澤井さんの夫が、アイデアマンということもあり、
多摩織は新しい可能性をどんどん広げているようです。
たとえば、ニューヨーク近代美術館の通販サイト「MoMA STORE」に写真のようなストールを出展したり、
生地が毛羽立たないようにするために、
普通の人では思い浮かばないような突飛な事を実際に試してみたり。
澤井さんはそんな夫と一緒にモノづくりをしていることが、
とても幸せそうに見えました。
続いて、伊万里・有田焼の作り手さんにお話をしていただきました。

伊万里・有田焼の青木妙子さん
青木さんは伊万里・有田焼の中でも、
鍋島焼を専門に作っています。
鍋島焼は佐賀藩の御用窯で、
献上用に作られていました。
青木さんは家族で焼き物をしており、
ろくろ、下絵、上絵などそれぞれを分担して作っています。
両親からも、兄弟仲良くすることが大事だと言われ、
今でも一緒に仕事をし、一緒にご飯を食べているとおっしゃっていました。
続いて、備前焼の作り手さんにお話をしていただきました。

備前焼の川井明美さん
川井さんはお母様の後を継いで、
備前焼の窯元になりました。
備前の土は、田んぼの下の土を使っています。
現在はもう取れなくなっていますが、
備前焼の窯元はみな、
工房に何十年分の土を寝かせているそうです。
備前の土には特徴があり、
とれたての土を使うことはありません。
野ざらし、雨ざらしをして2、30年ぐらい寝かせてから、
使うのが常識。
寝かせている期間も長ければ長いほど、
良い土になるとおっしゃっていました。
窯は登り窯で、
年に一度炊きます。
炊くときは十昼夜。
24時間体制で、何人かで窯の見張りをしながら炊き続けます。
ただ最後の2日間は、
火の止め時を見極める必要があるので、
交代はせずに川井さんが見張りをしているのだと、
おっしゃっていました。
最後に、もう一人の備前焼の作り手さんにお話をしていただきました。

備前焼の高見勝代さん
高見さんは初めから備前焼をしていたわけではなく、
絵描きでした。
ヨーロッパにも渡り、
本格的に絵の勉強をしていたものの、
壁を感じて地元の備前に戻ってきたそうです。
その時に、そういえば昔から備前焼が好きだったと気づき、
この世界に入ったと、おっしゃっていました。
高見さんの登り窯は、
年に一度10月1日から十昼夜炊きます。
備前焼には釉薬はつけません。
絵も施しません。
だからこそ、
焼き方一つで表情が変わるというのが楽しいそうです。
これからも、
色々な焼き方で、
色々な表情を見せてくれる備前焼を作り続けていきたいと、
おっしゃっていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回お話しして頂いた作り手さん達を含め、
合計24人の企画展「女一代のわざ 女性伝統工芸士展 作家とともに」は、
1月24日まで行っています。
ぜひ、足を運んでみてください。