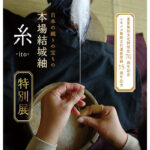青山スクエアでは11月11日(金)より、
特別展「香川漆器ぬり・もの・がたり」と匠コーナー「盛岡の伝統工芸品展~美しい技と心、岩手山麓に育まれ~」が始まり、
同日16時よりトークショーが行われました。
まず初めにお話をしていただいたのは香川漆器の匠です。

香川漆器の北山さん
香川漆器の代表的な手法は、
蒟醤(きんま)・存清(ぞんせい)・彫漆(ちょうしつ)・後藤塗(ごとうぬり)・象谷塗(ぞうこくぬり)の5つです。
北山さんは存清を得意としており、蒟醤との手法の違いを教えていただきました。
蒟醤は塗り重ねた漆に彫りを入れてから、その溝に漆を入れて研ぎだすため、出来上がりの表面は平らでツルツルとしているのが特徴です。それに対して存清は絵を描いてから絵の周りに細かい線をつけ、そこに金を入れたりするため、表面はデコボコしているのが特徴だそうです。
また今回、彫漆で作った花器も持ってきていただきました。

炎をイメージして作られたこの作品は、
乾漆で作られたものです。
乾漆は、麻布と漆だけで作るもののため、
木で出来た土台に漆を重ね塗るものと比べると非常に軽いのが特徴。
木で作ったものになると、
どうしても木目があったりして思うがままの形にすることができなかったりもするのですが、
乾漆は自分の思うような形をそのまま表現できるので、
北山さんはこの手法を取り入れているそうです。
さらに漆は、接着剤としての役割だけでなく、防水や殺菌効果もあるため、
長く使うことができるとおっしゃっていました。
続いて、浄法寺塗の匠にお話をうかがいました。

浄法寺塗の勝又さん
浄法寺塗といえば、
日本一の国産漆の産地として有名です。
国産漆はほとんど出回らなくなったと言われていますが、
浄法寺ではまだまだたくさんの漆の採れる木が存在しています。
ですが、漆の掻き手(木から漆を採る人)不足のため、
採れる量が減っているのが事実です。
今も掻き手を募集をしているそうですが、
中々人は集まらないそうです。
浄法寺塗の食器は普段使いのものがほとんどで、
購入したばかりの時はくすんだ色をしているのも特徴。

ですが、何年も使っているうちに、
艶が出るようになり光り出すと言います。
実際に、光っているお碗も持ってきてくださいました。
本当に同じものなのか・・・と思うぐらいに、
輝いているお碗は綺麗でした。
普通に使っていると、
8年ぐらいしないと輝いてこないそうなのですが、
毎日お碗をからぶきしていると、
1年でも光沢が出てくるそうです。
また、漆についての扱い方についても話していただきました。
漆が使われているものは、
使用後につけ置きをしないことが大前提です。
漆自体は防水効果があるので問題はないのですが、
器というのは知らず知らずのうちに小さな傷をつけていることがあり、
そこから水が入り込み、中の木にしみこんで、
木が膨張して漆が剥がれ落ちてしまうという現象がおこります。
ですので、なるべく長時間水にさらさないほうがいいというわけです。
漆の器を使用したら、
中性洗剤を柔らかいスポンジにつけて洗い、からぶきをしてあげるのが一番だとおっしゃっていました。
さらに、漆のものは、
10年に1度ぐらいの割合で、塗り直しをするのがいいそうです。
漆は重ねて塗れば塗るほど、
丈夫にもなっていきますので、
何十年も使い続けるのであればメンテナンスもしてみてください。
ーーーーーーーーー
今回お話をしてくださったお二方の作品が出展されている、
特別展「香川漆器ぬり・もの・がたり」は11月23日まで、
匠コーナー「盛岡の伝統工芸品展~美しい技と心、岩手山麓に育まれ~」は11月16日まで行われています。
ぜひ、青山スクエアまでお越しください。