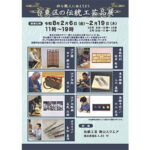今日から特別展「<ふじのくに>に伝わる伝統の技 静岡県の伝統工芸品展」と匠コーナー「〜五明が奏でる縁付け金箔の世界とミニ体験〜」が始まり、
14時からは青山スクエアでトークショーが行われました。
まずは駿河竹千筋細工の黒田さんにお話を伺いました。

駿河千筋細工の黒田倫世さん
駿河千筋細工は、
ヒゴを編んで作るのではなく、くみ上げて作るというのが特徴。
ひごは真っ直ぐなものなので、普通に曲げると折れてしまうものです。
曲げる時は熱を加えて柔らかくし、柔らかいうちに形を作っています。
また代表的なものと言えば、
虫かごや茶器入れなのですが、
最近は駿河千筋細工のバックも定番の一つに入ってきました。
女性用から男性用まで様々なタイプのものがあります。
現在作り手は11名おり、
その中で伝統工芸士は5名しかおりません。
ですが、以前に青山スクエアで特別展を行った時に、
駿河千筋細工を気に入ってくれた若手が4名、
現在修業をしている最中だそうです。
地元から若手を迎えることは出来なかったものの、
こうやって展示会を行うことで、
広く知ってもらうことができ、
後継者になりたいという人が現れたのはとても喜ばしいことだとおっしゃっていました。
次にお話しいただいたのは、
駿河指物の大間さんです。

駿河指物の大間晁さん
駿河指物は指物ということで、
釘を使わずに組み立てていくのが特徴です。
大間さんは既成概念にとらわれず、
ご自身のオリジナル作品を作り続けています。
作っているものも、日常の生活用品や茶道具、その他と、
一つのジャンルに絞っていません。
駿河指物は天然の木を使っているので、
使う際には湿度に気を付ける必要があります。
湿度は高すぎても駄目ですし、
クーラーを当てて湿度をなくしてしまうのも駄目です。
長く使うのであれば、
やはり置く場所には気を付けた方がいいそうです。
また駿河指物は、
その昔100近くの事業所がありましたが、
現在は2事業者しかいなくなってしまいました。
それでも、大間さんは県とタイアップして新しいものを考案したり、
季節に合わせて新作を出したりと、
常に前向きな姿勢で取り組んでいるとおっしゃっていました。
続いて掛川手織葛布の川出さんにお話をしていただきました。

掛川手織葛布の川出千通さん
掛川手織葛布は葛蔓を採取し、
それを繊維にしてから糸を作り、
そして織るという工程を踏みます。
昔は分業制で繊維を作る人、糸を作る人、織りをする人で分かれていたそうですが、
現在は作り手がほとんどいなくなってしまったため、
全ての工程を自分たちで行うようにしているそうです。
葛は一年草で、
一年で成長し最後には種子を土にばらまいでから枯れてしまう植物。
そのため、葛を採取するのは毎年6月~8月ごろです。
近くの山に生えているものなので、
特に栽培をしたりはしないとおっしゃっていました。
川出さんは6代目なのですが、
掛川手織葛布の作り手の中では一番若手です。
というのも現在作っているのは、二軒だけ。
今のままでは最後の作り手となってしまう危険があるので、
今後どうしていこうかと考えているそうです。
掛川手織葛布のなかで古くから作り続けられているのは掛け軸で、
最近は小物類も作るようになりました。
掛川手織葛布は染めをしてこなかったので、
地味な色味のものが多く、
最近は染めたものも販売するようにして若い層へのアピールもしています。
また葛はもともと汚れに強いという利点があるため、
長く使える物だとおっしゃっていました。
最後にお話しいただいたのは、
京仏具の五明さんです。

京仏具の五明久さん
京都では現在金箔を作っていませんが、
金箔を使う技術には長けているとおっしゃっていました。
使う技術というのは加飾することでもあり、
いかに金箔を活かして美しく見せるかということでもあります。
五明さんのいう金箔の美しさは、
もともとの金箔の色味風合いと同じ状態でものをつくるということ。
そのため五明さんは、あえて光沢を抑えるような仕上をしていると、おっしゃっていました。
ただ現在は、
お皿や笹の葉などに金箔を施すということをしていますが、
京仏具としての伝統技術を他のものに転用するだけではなく、
転用したものを見てもらって、
こんなに素晴らしい金箔貼りの技術が日本にあるんだということを知ってもらい、
京仏具への関心に戻すことを考えているそうです。
日本及び世界の文化財への対応を求められた時、
自分たちがその技術をしっかり提供できる出来る立場でありたいとおっしゃっていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
今回お話しいただいた、
特別展「<ふじのくに>に伝わる伝統の技 静岡県の伝統工芸品展」は9月20日まで、
匠コーナー「〜五明が奏でる縁付け金箔の世界とミニ体験〜」は9月13日まで行っています。
匠による実演や体験もありますので、
ぜひ青山スクエアにお越しください。